
請求書は、商品やサービスを提供した際に、その代金を顧客に請求する正式な書類です。これは、自社の売上を管理し、税務申告を行い、取引先との信頼関係を築く上で非常に重要な役割を果たします。特に、2023年10月1日から始まったインボイス制度により、請求書に記載すべき内容が更新されました。定められた必須事項を満たした請求書は「適格請求書」として扱われ、消費税の仕入税額控除に利用することが可能です。

ビジネスの現場では、請求書の他に、見積書、契約書、発注書、納品書など、多種多様な書類が用いられています。
見積書: 契約前に、おおよその費用を示す参考資料として提示されます。
契約書: 契約内容を明確にする法的効力を持つ文書です。
発注書: 商品やサービスの注文を正式に依頼する際に使用します。
納品書: 商品やサービスが確かに納品されたことを知らせるための書類です。
これらの書類は、取引の各段階において異なる役割を担い、円滑で透明性の高い取引を実現するために欠かせません。中でも請求書は、取引の最終段階で特に重要であり、正確な情報記載と適切な管理が求められます。請求書は売上の根拠となるだけでなく、健全な財務体質を維持し、ビジネスの信頼性と効率性を向上させるための重要なツールです。

請求書には決まった形式はありませんが、必要な情報を正確に記載することが大切です。以下に、請求書に必ず含めるべき主な項目をまとめました。
請求書の送付先となる会社名、部署名、そして担当者名を正確に記載します。敬称については、個人宛には「様」、会社や団体宛には「御中」を使うのが一般的です。ただし、「株式会社○○御中△△様」のように、両方を同時に使用することはできません。もし届けたい相手が会社内の代表者など、個人名宛に送る場合は、会社名の下の御中は省略し、「株式会社○○ △△様」と記載します。また、個人名の後に役職と様を並べて書くことはマナー違反とされていますので、役職の記載位置にも注意が必要です。

請求書をスムーズに管理するために、固有の識別番号を割り当てます。この番号によって、請求状況の追跡や内容の確認が格段に楽になります。もし、請求書を番号で管理していない場合は、特に記載する必要はありません。
請求書を発行する側の情報、つまり個人事業主または法人の情報を記載します(氏名または屋号、住所、電話番号、メールアドレスなど)。屋号をお持ちの場合は、氏名の代わりに屋号を記載することも可能です。ただし、振込先が個人名義になっている場合は、請求書と送金先を照合しやすいように、屋号と個人名を併記することをおすすめします。

請求書を作成した日付を記載します。取引先からの要望があれば、それに合わせて記入してください。
取引先と合意した支払期限を明確に記載します。支払いの遅延を防ぐために、具体的な期日を明記することが大切です。例えば、月末締めの翌月末払いの場合、4月分の請求書であれば「〇〇年5月末日までに下記口座にお振込みください」や「支払期日:〇〇年5月末日」のように記載します。
納品した商品や提供したサービスについて、その詳細な内訳、数量、単価、そして金額を漏れなく記述します。もし取引ごとに注文番号などを発行している場合は、「〇〇サービス(注文番号:1234567)」のように、関連する番号を併記することで、内容がより明確になります。
請求金額に課される消費税額を明確に記載します。軽減税率が適用されるケースでは、税率ごとに区分けして記載する必要があります。例えば、10%対象となるものと8%対象となるものをそれぞれ分けて、それぞれの税率ごとに合計した金額を示し、取引内容が「飲料品」など軽減税率が適用されるものであれば、その旨を明記します。

振込先の銀行名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義を間違いのないように記載します。振込手数料を相手に負担してもらう場合は、その旨をはっきりと記載します。継続的な取引がある相手であっても、振込先情報は毎回記載するように心がけましょう。銀行名、支店名、口座番号に加えて、口座種別や名義についても必ず記載してください。口座名義は「姓 名」のように、カタカナで記載するとより分かりやすくなります。
支払いに関する条件、振込手数料の負担、その他取引に関する特別な取り決め事項があれば、ここに記載します。もし振込手数料を取引先に負担してもらう場合は、「誠に恐縮ですが、振込手数料は貴社にてご負担をお願い申し上げます」といった文章を記載してください。
2023年10月から始まったインボイス制度に対応するためには、適格請求書発行事業者として登録を行い、次の項目を請求書に記載することが求められます。
インボイス制度に対応することで、取引先が仕入税額控除を利用できるようになり、ビジネスチャンスの拡大に繋がります。
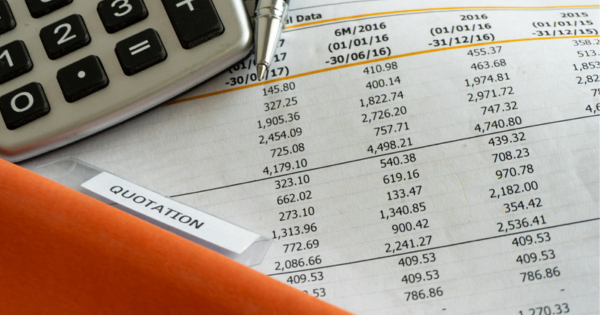
個人事業主が請求書を作成する際には、以下の点に注意を払う必要があります。
請求する金額に間違いがないか、入念に確認しましょう。Excelなどの自動計算ツールを使用している場合でも、計算式に誤りがないか、入力ミスがないかをチェックすることが大切です。金額の表記は「1,000円」でも「¥1,000-」でも、どちらでも構いません。しかし、「1000円」のような記載は避けてください。桁区切りは必ず入れるようにしましょう。
報酬の種類によっては、源泉徴収が必要となる場合があります。源泉徴収が必要な場合は、源泉徴収額を差し引いた金額を請求金額として記載します。以下に、所得税の源泉徴収が義務付けられている報酬の例を挙げます。
所得税の源泉徴収が義務付けられている報酬例
源泉徴収の対象となる報酬に関する請求書では、取引先が実際に支払う金額は、源泉徴収額を差し引いた後の金額となります。そのため、このような請求書を作成する際は、税抜き報酬金額に消費税額を加算し、合計の税込金額の下に源泉徴収額と請求金額を明記すると良いでしょう。
この際、源泉徴収額は税抜き報酬金額に所定の税率を掛けて算出します。
例:10万円の原稿料を請求する場合の請求合計額
10万円 - 1万210円 + 1万円 = 9万9,790円
例:200万円の出演料を請求する場合の請求合計額

サービス提供後、または契約で定められた期日に、迅速に請求書を作成し、顧客に届けます。送付手段としては、郵送またはEメールが一般的です。現在、ビジネスシーンにおいて請求書をEメールで送ることは広く普及しています。ただし、Eメールで請求書を送る前に、相手方にEメールでの送付が可能かどうかを必ず確認しましょう。事前の確認なしにEメールを送ることは、ビジネスマナーに反する行為とみなされます。郵送と比較して、Eメールは印刷コストや郵送コストを削減でき、即座に相手に届くため、確認がスムーズになります。Eメールで請求書を送信する際は、内容の改ざんを防ぐためにPDF形式に変換して送ることが一般的です。PDFファイルを送付する際には、パスワードを設定したり、請求書管理システムを利用するなど、セキュリティ対策を講じることが重要です。
発行した請求書の控えは、税法に従い一定期間保管することが義務付けられています。法人の場合は7年間、個人事業主の場合は原則として5年間保管する必要があります。請求書を年度ごとに整理するなど、管理しやすいように工夫することが大切です。紙媒体で発行した請求書の控えや受領した請求書は、従来通り紙で保管できますが、電子帳簿保存法の改正により、電子的な取引を通じて発行・受領した請求書は、電子データの形式で保管する必要があります。請求書の発行方法や受領方法によって保管方法が異なるため、注意が必要です。
請求書作成の方法は、テンプレートの使用、WordやExcelでの自作、請求書作成アプリや会計ソフトの利用など多岐にわたります。自社の状況やニーズに最適な方法を選択し、請求業務を効率化しましょう。
インターネット上で提供されている様々な請求書テンプレートを利用することで、手軽に請求書を作成できます。
WordやExcelを利用して、自社のニーズに合わせた請求書を独自に作成することもできます。請求データの保護を考慮し、作成したファイルはPDF形式に変換し、メールで送信することをおすすめします。前述したように、PDF化は改ざんを防ぐ有効な手段です。
請求書作成に特化したアプリケーションや会計ソフトウェアを利用することで、請求関連の作業をより効率的に進めることができます。見積書や納品書といった書類も取引ごとに作成でき、電子印鑑をソフト内で押印できる機能が搭載されているものもあります。

請求書は、取引先との良好な関係を維持するために非常に大切です。丁寧な言葉を使うこと、誤字や脱字がないか確認すること、適切な方法で送付することなど、ビジネスにおける基本的なマナーを守り、請求書を作成し送付しましょう。
請求書は原則としてA4サイズの用紙を使用します。封筒に入れる際は、三つ折りが基本とされています。封筒を開封した際に、請求書の冒頭部分が最初に目に入るように、表面を上にして、まず下から3分の1を折り、次に上の3分の1を折って封入します。
個人宛に請求書を送る場合は「様」を、会社、役所、各種団体宛の場合は「御中」を使用します。「○○株式会社御中△△様」のように、両方を同時に使うことは誤りです。会社の代表者など、個人名が分かっている場合は、会社名の後に「御中」は不要で、「○○株式会社△△様」とします。
署名の最後の文字に少し重ねて押印するのが基本です。文字から離れた場所に押印すると、後から改ざんされるリスクがあると判断され、正式な請求書として認められない場合があります。請求書への押印で迷うのが、印鑑を傾けるかどうかです。正式な書類である請求書には、印鑑をまっすぐに押すのが適切です。印影が傾いていると、不注意な印象を与え、書類の信頼性を損なう可能性があります。ただし、慣習的に認印や訂正印を押す場合は、意図的に少し傾けて押すことがあります。これは、正式な実印との区別のためという考え方に基づいています。重要なのは、傾き具合よりも、印影が鮮明であるかどうかです。「印影に欠けがないか」「インクが滲んでいないか、薄くなっていないか」「印影が判読可能か」といった点をしっかり確認しましょう。これらは、丁寧さだけでなく、書類の信用性にも関わる重要なポイントです。
請求書をメールで送付することは、現代のビジネスシーンでは一般的になりつつあります。ただし、事前に取引先へメールでの送付が可能かどうかを確認することが重要です。事前の確認なしにメールで送付するのは、マナー違反となる場合があります。メールでの送付は、郵送に比べて印刷代や郵送代が不要で、迅速に相手に届くため、確認作業をスムーズに進めることができます。請求書をメールで送る際は、内容の改ざんを防ぐため、PDF形式に変換して送付するのが一般的です。PDFファイルにパスワードを設定したり、請求書管理システムを利用するなど、セキュリティ対策を講じることが重要です。メールの本文には、以下の情報を記載すると丁寧です。1. 挨拶文 2. 請求内容の概要(金額、支払期限など) 3. 添付ファイルの確認を促す一文。添付する請求書のファイル名は、自動生成されたものではなく、発行日などを記載して、取引先が内容を把握しやすいように工夫しましょう。請求書は重要な情報が記載された書類です。送信前には、宛先のメールアドレスに誤りがないか、再度確認するようにしましょう。
請求書を送付する際には、添え状を同封するのが礼儀です。添え状には決まった形式はありませんが、時候の挨拶や日頃の感謝の気持ちを伝え、請求に関する要件を簡潔に記すのが一般的です。添え状に書類の総枚数を記載することで、請求書の内容に誤りがないか、双方で確認しやすくなります。添え状に記載すべき項目としては、「送付日、送付先の宛名、差出人の氏名、時候の挨拶、日頃の感謝、請求書の枚数」などが挙げられます。添え状の文章をゼロから作成する必要はなく、インターネット上で提供されているテンプレートを参考に、自社の状況に合わせてカスタマイズすると良いでしょう。
本記事では、個人事業主やフリーランスの皆様が請求書を作成する上で不可欠な情報と具体的な方法について詳しく解説しました。正確な請求書を作成し、それを適切に管理することは、円滑な取引を実現し、健全な事業運営を支える上で非常に重要です。
請求書の宛名、請求内容の詳細、消費税額、そして発行日などが必須項目となります。詳細については、上記本文中で詳しく解説していますのでご確認ください。
金額の正確な記載方法、消費税の取り扱い、源泉徴収税の有無など、注意すべき点は多岐にわたります。これらの詳細についても、上記本文中で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
はい、その通りです。インボイス制度に対応した請求書を作成する必要があります。必要な記載内容などについては、上記本文中で詳しく解説していますので、必ずご確認ください。