
見積書は、これから商品やサービスを提供する予定の顧客に対して、契約を行う前に提示する書類です。この書類には、提供する商品やサービスの詳細、数量、それぞれの価格、合計金額、納期、そして見積もりの有効期限などが記載されています。顧客はこれらの情報をもとに、契約を結ぶかどうかを判断します。通常、見積書は発注者からの依頼を受けて作成されますが、後々のトラブルを防ぐために、発行側から積極的に提案することもあります。

見積書は、契約前の段階で、提供する商品やサービスにどれくらいの費用がかかるかを伝える書類です。一方、請求書は、契約に基づいて商品やサービスを提供した後、実際に発生した費用を記載し、支払いを求めるための書類です。見積書はあくまで予想される費用を示すものであり、実際の金額と異なることもありますが、請求書は確定した金額に基づいて発行され、支払いの根拠となります。請求書がないと、たとえわずかな金額であっても支払ってもらうことはできません。また、請求書は支払い状況や金額の確認にも使われるため、きちんと保管しておくことが重要です。

見積書を発行する主な理由は、以下の3つです。
さらに、見積書を作成することで、金額の内訳が明確になり、提示した金額の根拠を示すことができます。口約束だけの取引は後々トラブルにつながる可能性があるため、見積書は受注側、発注側の双方にとって、認識のずれをなくすために不可欠です。見積書は取引の証拠となる重要な書類であり、法人の場合、原則として7年間、欠損金が発生した場合には10年間の保存が義務付けられています。
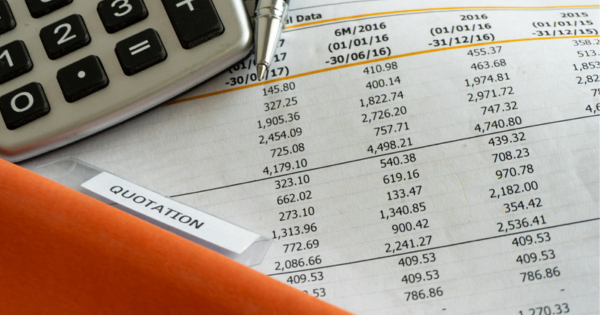
通常、見積書は取引の最初の段階で作成される書類です。代金を後で支払う「掛取引」の場合、まず見積書を提示し、双方が合意すれば発注、納品、検収という流れになります。その後、請求書を送付し、代金が支払われ、領収書が発行されて取引が完了します。
見積書に定められたフォーマットはありませんが、以下の情報を盛り込むことで、取引先は内容をスムーズに把握できます。
上記の情報を記載することで、発注側は見積内容を正確に理解し、発注判断を円滑に進めることができます。

ここでは、見積書を構成する各項目の書き方を詳しく説明します。会計ソフトのテンプレートなどを参照しながら、具体的な記入方法を確認していきましょう。
見積書の表題は、内容をすぐに理解できるように、「見積書」「お見積り書」「御見積り書」などと記載します。
見積もりを依頼してきた取引先の正式名称を記入します。依頼者が企業の場合は社名の後に「御中」を、個人の場合は氏名の後に「様」を記入します。部署や担当者の指定がある場合は、部署名や担当者名も忘れずに記入します。
宛名欄には、取引先の郵便番号と住所も併せて記入しましょう。

見積書を作成した日付を見積日として記載します。見積番号(連番)は必ずしも必要ではありませんが、番号を付与して検索性を高めることで、見積書の検索や再発行などの社内管理を効率化できます。番号を付与する際は、管理しやすいように、同一の契約に基づいて発行される他の書類(請求書や納品書など)と共通の番号体系を用いると良いでしょう。
見積書の有効期限を設定することに、法律上の義務はありません。有効期限は業界によって異なりますが、一般的には2週間から6ヶ月の間で設定されることが多いです。有効期限を定めることで、取引先の契約意欲を促したり、将来的な商品やサービスの価格変動に備えることができます。
有効期限の開始日を見積日とする場合は、見積日を再度確認することを忘れないようにしましょう。

見積書の発行元となる会社名(または個人名)、住所、電話番号などの情報を記載します。担当者情報としては、取引先からの見積もりに関する問い合わせに対応できる担当者の連絡先を明記します。捺印は必須ではありませんが、捺印する場合は、会社名や担当者情報に一部重なるように会社の角印を押すのが一般的です。改ざん防止などの理由から捺印を求められる場合もあるため、事前に取引先に確認しておくと良いでしょう。電子見積書を発行する際には、捺印の代わりに電子署名を使用します。
商品・サービスの詳細、数量、単価、金額をそれぞれ記載します。商品・サービスの詳細欄には、具体的な内容がすぐに理解できるように記載することで、取引先が具体的な検討を進めやすくなります。
小計、消費税額、そして最終的な合計金額を明確に記載します。専用の会計ソフトウェアと連携可能なテンプレートを使用すれば、商品ごとの単価と金額を入力するだけで、自動的に合計金額が算出される便利な機能もあります。見積書をインボイス(適格請求書)として利用するケースは一般的ではありませんが、発行者が適格請求書発行事業者である場合、税込み・税抜き表示、適用される消費税率、登録番号などを記載することで、インボイスとしての要件を満たすことが可能です。もし納品書の記載内容だけではインボイスの必要条件を満たせない場合でも、見積書と合わせて記載することで、必要な情報を補完できることがあります。
支払いに関する条件や納期など、見積もりに関する重要な特記事項があれば、備考欄に詳細を記入します。見積書を作成する上での前提条件や、見積金額に変更が生じる可能性のある事項についても、必ず明記するようにしましょう。
【備考欄の記載例①(制作において発注者の協力が必要な場合)】本見積書は、弊社が指定の期日までに成果物を納品することを前提としており、そのためには、発注者様からの必要な素材のご提供、迅速な承認作業、その他、発注者様の誠実なご協力が不可欠となります。
【備考欄の記載例②(再見積もりが必要となる条件を明示する場合)】本見積書に記載されていない事項、または仕様や条件に変更があった場合には、改めてお見積もりをご提示させていただきます。

見積書は、以下の手順で作成し、送付します。
見積書の作成方法としては、手書き、ExcelやWordを使用する方法、専用の会計ソフトウェアを利用する方法などがあります。近年では、業務効率の向上や管理の容易さから、電子データによる作成が主流となっています。
ウェブ上には、表計算ソフトやワープロソフトで利用できる無償の見積書フォーマットが豊富に公開されています。これらのフォーマットを活用すれば、容易に見積書を作成できますが、内容の改ざんを防ぐため、PDF形式や画像形式で保存することを推奨します。
経理ソフトを使用すれば、見積書に加え、請求書や納品書などの書類もスムーズに作成できます。多くの経理ソフトには雛形があらかじめ用意されており、必要な情報や金額を入力するだけで見積書が完成します。さらに、見積書から請求書への自動変換機能など、事務作業の効率化を支援する機能が搭載されているものもあります。
見積書を電子データとして作成し、送付する際は、見積書のフォーマットがあればすぐに作成に取り掛かれます。作成が完了した見積書は、メールやチャットツールに添付して送付する、印刷して手渡しする、またはFAXで送信するなどの方法で相手に届けます。紙媒体で郵送する場合は、封筒と切手を用意し、封筒には「見積書在中」と明記することが重要です。
見積書を作成し、保管する際には、以下の点に留意する必要があります。
令和5年10月に始まったインボイス制度では、適格請求書(インボイス)の保管が求められます。通常、見積書がインボイスとして扱われることは少ないものの、登録番号を記載しておくことで、後々の請求書との照合が容易になります。
見積書は、法人では7年間、個人事業主では5年間の保存が義務付けられています。電子帳簿保存法の改正に伴い、電子データとして受け取った見積書は、原則として電子的な形式での保存が必須となります。

納品時期や支払い条件など、後々問題が生じやすい事項については、見積書に明確に記載することが大切です。これにより、誤解や認識のずれを防ぎ、円滑な取引に繋げることができます。
見積書には有効期限を明記することで、提示された見積金額や内容がいつまで有効であるかを明確にします。これにより、見積提出後の価格変動や条件変更によるトラブルを回避できます。
見積書は、商取引における最初の重要なステップとなる書類です。正確な情報を分かりやすく記載することで、円滑な取引へと繋げることが可能です。テンプレートや会計システムを効果的に利用し、効率的な見積書作成を目指しましょう。
見積書には、商品やサービスの価格、数量、提供範囲、発注者の情報、自社の担当者名や連絡先など、見積もり段階で発注者側が必要とする情報を網羅的に記載します。詳細については、記事内の「見積書の作成に必要な項目」のセクションで詳しく説明しています。
見積書の形式は、ExcelやWord、市販の専用ソフトウェア、または会計システムを使用して作成するのが一般的です。特に会計システムを利用すれば、必要な情報を入力するだけで簡単に見積書を作成できるだけでなく、請求書や納品書などの関連書類の発行・管理、さらには会計処理にも対応できます。詳細については、記事内の「見積書の作成方法:テンプレートとシステム」をご参照ください。
見積書の有効期限は、扱う業界や提供する商品・サービスの種類によって適切な期間が異なります。一般的には、2週間から半年程度の間で設定されることが多いようです。特に、市場の価格変動が大きい商品やサービスを提供する場合は、有効期限を短めに設定することが推奨されます。